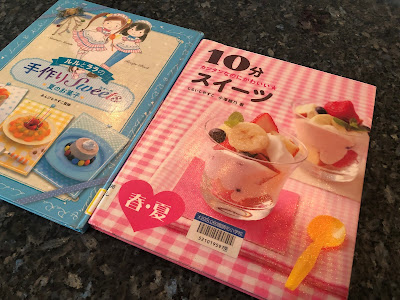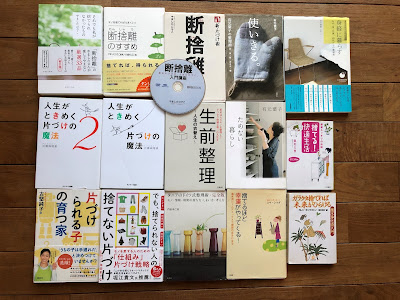自分の生活圏にある行きつけの店がなくなるのは、とても寂しいものです。子どもたちが大好きだった駄菓子屋さんが先日、ひっそりと閉店しました。息子が教えてくれました。
「ママ、駄菓子屋さんが閉まるらしいよ。コロナだからっておじさんが言っていた」と息子が教えてくれたのはこの水曜日。いつものように小銭を持って、その駄菓子屋さんに行って帰ってきて、そう報告してくれました。
「えっ? 閉まるってずっと? それともコロナが収まるまで?」
「わからない」
「どうして、そういう重要なことをきちんと聞いてこないの!」と思わず息子に声を荒げてしまいました。私は明らかに動揺していました。
翌日の木曜日の夜に行ってみると、シャッターが閉まっていました。シャッターの横に小さな紙が貼ってありましたが、よく見えませんでした。で、今日の夕方改めて、息子と娘と行ってみました。張り紙にはこう書いてありました
「閉店 本当にありがとうございました。駄菓子屋」
 |
| 閉店を知らせる駄菓子屋さんの張り紙 |
「本当に閉まっちゃったみたいだよ」と子どもたちに言うと息子が肩を落として言いました。
「魂ぬけた…」
息子はこの駄菓子屋さんが大好きで、2日に1度は通っていました。ガムが1個11円と安いので、50円あればガムが4個買えるのです。私にはいつもキャラメル1個を買ってきてくれました。お友達の家に行くときも、ここから手土産を買って持って行っていました。
「いつもここにあったのに、寂しいね」と娘。
「100円でいくつ買えるかな」。子どもたちはここで計算を覚えました。遠足のときも、ここでおやつを買いました。夏になると冷えたラムネを買って、店先にある古いベンチに座って子どもたちと一緒に飲みました。
息子にせがまれて買った仮面ライダーのお面。息子と一緒にドッチボールをした虹色のボール。縄跳びも、お寿司やケーキの形をした消しゴムもここで買いました。38円のポテトチップスはとてもおいしかった。1個がとても酸っぱい3個入りのガムを買って、娘と息子とじゃんけんをして選んで食べたっけ。
子どもたちとのたくさんの思い出が詰まった駄菓子屋さんが、なくなってしまうなんて…。
ここは私の小さなころの、幸せな思い出の場所ととても似ていました。札幌生まれ札幌育ちの私ですが、幼稚園のころ、たぶんほんの半年ほど北海道の浜松町という町に住んだことがあります。建設会社に勤めていた父の仕事の関係で、しばらくそこに住んだのです。
私たちが住んでいた家の近くに駄菓子屋さんがありました。そこで売っていたヨーグルト味のお菓子と同じお菓子が、ここの駄菓子屋さんで売っていたのです。それを見るたびに、幸せだったそのころを思い出していたのです。
寂しくてたまりません。考えると落ち込むので、なるべく考えないようにします。