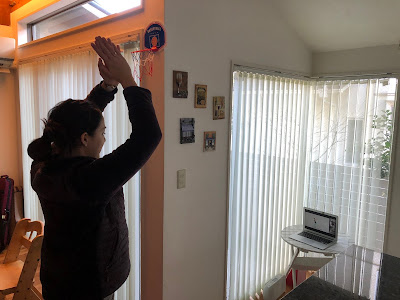片付け本を何冊も読んでいると、いくつかの共通点を探すことが出来ます。一つは、引き出し一つなど小さなところから始めるよう勧めていること。そして、「納戸」は最初に片付けると挫折する可能性が高いので、最後に取り組むよう勧めていることです。
私はあまのじゃくではないのですが、これまで10冊以上の片付け本を読んで成功しなかったので、邪道と呼ばれるところから始めることにしました。そうです。物を詰め込んでいる屋根裏部屋です。
我が家はキッチンとダイニング、そして寝室と娘の部屋、バスルームとトイレが一階にあり、2階はリビングになっています。リビングに私の仕事・勉強スペースがあります。そして、一階の屋根裏部分に息子の部屋があります。2階のリビングにドアが付いていますので、2階のような印象ですが、実は1階の屋根裏です。
その反対側にあるのが、納戸。ここにもリビングから入ります。スーツケースや寝具、小さくなった子どもたちの服や”作品”の数々、趣味の用品などぎゅうぎゅうに詰まった納戸から物を取り出し、収納ケースに収め直すことにしました。
もちろん、全部を出したら整理に何ヶ月もかかりそうですので、数日間で出来る分を出して、詰め直すという方法を取りました。収納ケースはこれまで使っていた、3段のカラーボックス8個、IKEAで買った幅40㌢奥行き60㌢高さ100㌢の収納ケース、ラタンのケース6個です。
リビングのテレビで「断捨離」の提唱者やましたひでこさんのDVDを流しながら、取り組むことにしました。
納戸の物を出してみて分かったのは、私はほとほと後ろ向きな人間なのだなということ。DVDの中でやましたひでこさんは、片付けられない人を「現実逃避型」「過去執着型」「未来不安型」の3タイプに分けています。やましたさんによると、この3つの要素は混在しているそう。自分がどのタイプか理解すると、断捨離は進むといいます。
「現実逃避型」は家にいないから家が片付かないパターン。家が片付いていないから家にいたくないので外に出るーだから片付かないという悪循環タイプ。「忙しい」「面倒くさい」が口癖だそうです。私は家にいるのが好きなので、これではないと思いました。
次が「過去執着型」。やましたさんが説明する理由の「買ったときに高かった」はあまりないかもしれませんが、「もったいない」はあると思いました。自分の努力の証拠となる学習教材やトロフィーなどの過去の栄光グッズはありませんが、子どもたちの思い出が詰まった物への執着は強い。この過去執着型が、物が一番手放しづらいタイプだそうです。
最後の「未来不安型」。今は必要ないけど、「また、いつか必要になるかもしれない」とため込むタイプ。このタイプが多いそうです。私は日用品のまとめ買いはしませんが、「箱」「紙袋」は捨てられません。私は何かを仕舞うときに、ちょうどいい大きさの空箱を探して収めることに喜びを感じるタイプ。また、私のような捨てられない人間が過去に使ったものを捨てるときには、”儀式”を必要とします。きれいな紙袋に入れて「ありがとう」と言って捨てるのです。ですので、きれいな紙袋は取っておきたい。
私はフイルムカメラ時代から写真を写すのが好きで、未使用のアルバムや写真立てなどもたくさん。カラーボックス3つ分ありました。そして、カラーボックスの箱の中に大量に押し込まれていたのがスクラップブッキングの材料。スクラップブッキングは写真を台紙に張り、飾り付けたり思い出をつづったりする手法です。アメリカの義妹が、私と夫の結婚式のアルバムをスクラップブッキングで作ってくれたことがきっかけで、趣味になりました。
 |
| 納戸にあったスクラップブッキングの材料 |
教室に通っていたのですが、病気をしてしまい中断。でも、材料は買い続けていました。義母も日本にくるたびに材料をお土産に持ってきてくれました。この材料を整理していて、「私はこれをしたかったんだな」と改めて思います。
また、子どもの物を作るはずだった生地やフエルト、毛糸などもIKEAの収納ケース1台分にいっぱい詰まっています。これもしたかったのですね。
 |
| 手芸用品を押し込んであるIKEAの収納ケース(後ろ) |
片付け本では趣味の物も今使っていないのなら処分するようにアドバイスしていますが、私は整理してきちんと仕舞いました。1月に合計16時間納戸の片付けに取り組みましたが、ほとんど捨てませんでした。もちろん、子どもたちの学校の教科書や道具を整理していたときに見つけた、娘の小学校のときのテスト用紙などは捨てました。が、ほとんどを整理整頓したという感じです。子どもたちの服は収納ケースに入れたり、カラーボックスに畳んで入れたり。
 |
| 畳んで仕舞い直した息子の服 |
これらはもう手放してもいいな、と思える日まで置いておこうと思います。捨てることは私の成長につながると思えないし、ましてや未来が開けるとも思えない。逆に捨てられないこれらの物をきちんと整理して仕舞うことが、私の心の安定につながると思うのです。なにせ、私は娘が着ていたドレスや外出着はクリーニングに出して保管しているほどの究極の捨てられない人間なのです。
息子が着ていた服でシミになっていたものは天気の良い日にシミ取りをして洗濯し、外干ししてIKEAのプラスチックの袋に入れました。シミを見つけた娘の夏用のドレスも、娘を抱いて寝ていたころ私が着ていたパジャマ(義母のプレゼント)も同様に洗って、外干しをして仕舞いました。
 |
| 息子が3歳ごろに着たTシャツ。洗い直して仕舞いました |
 |
| 洗い直して仕舞った娘のドレス(左)と私の思い出のパジャマ |
 |
プラスチックケースに仕舞った子どもたちの服。将来息子に”ウザい”と思われそうです
|
こういう作業をしていると、私は本当に物を処分できない人間だなと改めて思います。でも、無理をして処分をすると心が壊れてしまいそうな気がしますので、こういう自分を認めるしかないかと思う日々です。