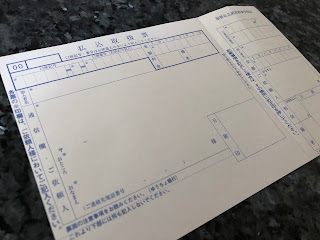昨日、郵便局に口座開設の申請をしました。読者の方から書店を通さず直接注文が来る事が増えたためです。
お電話をいただき、本をお送りするのは心躍る作業です。書店に注文される方々は本が書店に届くまでずいぶん時間がかかると聞いていましたので、こちらからお送りすれば数日でお手元に送れます。
課題は、代金をどういただくかにありました。立て続けに銀行や書店が近くになく、かつアマゾンなどネットで本を買う習慣がない方々から注文があり、そういう方々は本を買うのも、何かの代金を支払うのも難しいのだと気付かされたのです。私はいかに、銀行や書店が比較的近くにあり、かつ「ワンクリック」で物を買う生活に慣れてしまったのかと、痛感しました。
そうした理由で、小さな町や村にもある郵便局から振り込んでいただくのが一番良いのだろうと、さっそく昨日、書類をそろえて最寄りの郵便局に振替口座開設の申請に行ったのです。振替口座を開くと、「払込取扱票」で代金を請求でき、受け取った側もそれを使って代金を払い込むので手間がかからないようなのです。
口座開設のための提出書類の中に、会社の登記事項証明書があります。そこには、会社の事業内容が書いてあります。登記の準備をしていたとき、法務局の担当の方から「後から変更するのは大変ですので、将来計画しているものもとりあえず全部入れたほうが良いです」と助言をいただいたため、思い付くものを全部入れました。私の会社「合同会社まりん書房」の事業は次の8つです。
1) 書籍の出版
2) 雑誌の発行
3) 電子書籍の発刊
4) Web媒体の制作・運営
5) 記事・原稿の取材・執筆
6) 古書の販売
7) ブック・カフェの運営
8) 前各号に附帯関連する一切の事業
この登記事項証明書が、申請に行ったときに担当してくれた男性の郵便局員さんの心に響いたらしいのです。書類を見た郵便局員さんの目が輝いていました。
「ブック・カフェをされているのですか?」
「いいえ、本の出版で今のところ精一杯で、ブック・カフェまで出来るかどうか、、、。法務局の相談員の方も、登記について相談した方々も異口同音に思い付くものは全部入れたほうが良いと仰っていたので、とりあえず入れたのです」
私は苦笑しながら、言い訳じみた答えをしました。実際、本の出版は年に1冊できれば良いぐらいのペースで、5)の記事の取材・執筆以外は、取り組む余裕がありません。
が、その郵便局員さんは頬を紅潮させながら言いました。年齢はおそらく50代半ばから後半だと思います。いただいた名刺には「課長補佐」と肩書きがありました。
「私、定年後にブックカフェを開くのが夢なんです。映画カフェでもいいですし。カフェを開く準備のため、専門学校にも行きました」
「そうなんですか! 素敵な目標ですね。私はまだまだ本の出版で精いっぱいで、、、。でも、少しずつ取り組んでいきたいと思っています」
「また、いろいろ教えてください」
申請が終わり、郵便局を出ました。横に止めてあった自転車に乗って帰ろうとしたとき、裏のドアが開き、その郵便局員さんが出てきました。そして、ニコニコしながら、袋を渡してくれました。その中には、「クレラップ」と子ども向けの「ぬりえセット」が入っていました。胸にじんときました。
「どうぞ、使ってください。お子さんにも差し上げてください」
その郵便局員さんが私の携帯に問い合わせの電話をくれたときに、息子がたまたま答えたため、息子にもと気を遣ってくれたのでしょう。
郵便局員さんの笑顔は、私の心を和ませてくれました。将来、その素敵な夢が叶いますように、と心から願いました。
2019年5月28日火曜日
2019年5月27日月曜日
我が家のバターが減る理由
我が家はバターの減り方が早い。買い置きしていても、あっという間になくなります。買うのは「雪印北海道バター」。北海道生まれの私が子どものころから慣れ親しんだそのバターを今でも使っています。
我が家で一番バターを消費してきたのは私。昔から朝食にバタートーストを食べることが多く、中年になり和食を好むようになっても、朝はやっぱりバタートーストを食べたいのです。
国立がん研究センター中央病院でよくお見かけした政治家・故与謝野馨さんも、著書で「食パンの厚さに近いほどバターをたっぷり塗り、その上に砂糖をまぶして二枚食べる」と書いており、それ以来与謝野さんへの親近感が一気に増しました。
生活習慣病を気にして食べ物を制限するより、食べたいものを食べて体力をつけ、体重を落とさないほうががん患者にとって良いという考えに、私も大いに賛成しました。だから、私は50代になっても、バターをたっぶり塗ったトーストはやめません。
さて、昨年ぐらいから、我が家のバター消費量が一気に増しました。使っているのは、小2の息子です。息子はバタークッキー作りが大得意。分量もしっかり記憶していて、レシピを見なくても作れるのです。「家にお菓子がないから、クッキー作ろう!」と、さっと自分で作ってしまうほど、手慣れています。
昨日、お友達のお誕生日会にも持参しました。プレゼントは用意していたのですが、朝、「ゴム鉄砲」とバタークッキーを作ることを思い立ったようなのです。ユーチューブで作り方を見ながら人数分のゴム鉄砲(割りばしとゴムで出来ています)を作った後は、クッキー作りです。
作ったのは9枚。お誕生日のお友達とお母さん、お誕生日会に招待された4人と夫、娘、私にそれぞれ1枚ずつです。
小麦粉と砂糖、バターの分量を量り、バターを電子レンジで温めて柔らかくし、材料を混ぜてこねます。生地を少し冷蔵庫で寝かした後、手の平ぐらいの大きさに丸く平べったくし、クッキングシートを敷いた天板の上に並べます。型を使わないので、手作り感が出て、美味しそうに出来上がります。オーブンで焼くときの温度と時間も覚えているので、簡単。焼き上がって冷めた後、1枚1枚丁寧に袋に入れて、出来上がり。
思いがけず、お相伴に預かった私。その1枚を味わいながら、「世界で一番おいしいこのクッキーをこれからもずっと食べられますように」と心の中で祈ったのでした。
我が家で一番バターを消費してきたのは私。昔から朝食にバタートーストを食べることが多く、中年になり和食を好むようになっても、朝はやっぱりバタートーストを食べたいのです。
国立がん研究センター中央病院でよくお見かけした政治家・故与謝野馨さんも、著書で「食パンの厚さに近いほどバターをたっぷり塗り、その上に砂糖をまぶして二枚食べる」と書いており、それ以来与謝野さんへの親近感が一気に増しました。
生活習慣病を気にして食べ物を制限するより、食べたいものを食べて体力をつけ、体重を落とさないほうががん患者にとって良いという考えに、私も大いに賛成しました。だから、私は50代になっても、バターをたっぶり塗ったトーストはやめません。
さて、昨年ぐらいから、我が家のバター消費量が一気に増しました。使っているのは、小2の息子です。息子はバタークッキー作りが大得意。分量もしっかり記憶していて、レシピを見なくても作れるのです。「家にお菓子がないから、クッキー作ろう!」と、さっと自分で作ってしまうほど、手慣れています。
昨日、お友達のお誕生日会にも持参しました。プレゼントは用意していたのですが、朝、「ゴム鉄砲」とバタークッキーを作ることを思い立ったようなのです。ユーチューブで作り方を見ながら人数分のゴム鉄砲(割りばしとゴムで出来ています)を作った後は、クッキー作りです。
作ったのは9枚。お誕生日のお友達とお母さん、お誕生日会に招待された4人と夫、娘、私にそれぞれ1枚ずつです。
小麦粉と砂糖、バターの分量を量り、バターを電子レンジで温めて柔らかくし、材料を混ぜてこねます。生地を少し冷蔵庫で寝かした後、手の平ぐらいの大きさに丸く平べったくし、クッキングシートを敷いた天板の上に並べます。型を使わないので、手作り感が出て、美味しそうに出来上がります。オーブンで焼くときの温度と時間も覚えているので、簡単。焼き上がって冷めた後、1枚1枚丁寧に袋に入れて、出来上がり。
思いがけず、お相伴に預かった私。その1枚を味わいながら、「世界で一番おいしいこのクッキーをこれからもずっと食べられますように」と心の中で祈ったのでした。
2019年5月25日土曜日
国会図書館に納本
出版社を立ち上げてから、やる事なす事新しいことだらけで、仕事が追いつきません。そんな中、ずっと先延ばしにしていたことを一昨日の5月23日、ようやく終えました。国立国会図書館への納本です。
国や地方公共団体、それに準じる法人、出版社や学術団体らは「国立国会図書館法」に基づき、出版物を同図書館に納める義務があります。「納本制度」と言います。同図書館によりますと、納本の目的は官庁出版物については「政府活動に関する国政審議に役立てるため」、民間出版物は「国民共有の文化的資産として、広く利用に供し、永く後世に伝えるため」となっています。
「文化的資産」「広く利用に供し」「永く後世に伝える」・・・。自分の本がこのような目的で国会図書館に置いてもらえるなんて、こんな嬉しいことはありません。
納本は郵送でも出来るのですが、私は図書館に出向いてしたかった。そのため、少し遅くなってしまいましたが、図書館の担当者はとても丁寧に応対してくれました。手続きは所定の用紙に出版社名、住所など必要事項を記入するだけなので、あっという間に終わりました。
「いってらっしゃい。お役に立つんだよ」
担当者に手渡すとき、心の中でそう本に語り掛けました。本が私の手元から旅立つときは、いつもそう送り出します。「いってらっしゃい。頑張るんだよ」と子どもたちを朝、学校に送り出すときと同じ様に。
国や地方公共団体、それに準じる法人、出版社や学術団体らは「国立国会図書館法」に基づき、出版物を同図書館に納める義務があります。「納本制度」と言います。同図書館によりますと、納本の目的は官庁出版物については「政府活動に関する国政審議に役立てるため」、民間出版物は「国民共有の文化的資産として、広く利用に供し、永く後世に伝えるため」となっています。
「文化的資産」「広く利用に供し」「永く後世に伝える」・・・。自分の本がこのような目的で国会図書館に置いてもらえるなんて、こんな嬉しいことはありません。
納本は郵送でも出来るのですが、私は図書館に出向いてしたかった。そのため、少し遅くなってしまいましたが、図書館の担当者はとても丁寧に応対してくれました。手続きは所定の用紙に出版社名、住所など必要事項を記入するだけなので、あっという間に終わりました。
「いってらっしゃい。お役に立つんだよ」
担当者に手渡すとき、心の中でそう本に語り掛けました。本が私の手元から旅立つときは、いつもそう送り出します。「いってらっしゃい。頑張るんだよ」と子どもたちを朝、学校に送り出すときと同じ様に。
2019年5月24日金曜日
You make my day
英語のフレーズに「You make my day」という良い表現があります。直訳すると「あなたは私の一日を作ってくれた」。意訳すると、「あなたのおかげで、私の一日が素晴らしいものになったわ」です。
たとえば、あなたが落ち込んでいるとき、友人や彼があなたのことを褒めてくれた。もしくは、あなたの子どもや夫が、何気ない、でも素敵なプレゼントをくれることもあるでしょう。一日、仕事や家事・育児で疲れ切ったあなたは、その言葉や小さな贈り物でその日一日を幸せな気持ちで終えることが出来ました。そんなときに、相手に言う言葉です。
「You make my day」-。私はその言葉を最近2回、遠方に住むある人に言いたい気持ちになりました。2回とも、同じ人に対してです。
その人は、北海道利尻郡利尻富士町に住んでいます。4月27日に、北海道新聞に私のインタビュー記事が掲載されたとき、真っ先に電話をくれた人です。その人は記事を読み、拙著「がんと生き、母になる 死産を受け止めて」を読みたいと思ってくれたらしく、直接電話をくれたのです。記事には私の会社の連絡先が書いてありませんでしたので、北海道新聞か書店に電話をして、連絡先を尋ねてくれたのだと推測しました。
電話がきた土曜日の午前中、私は大学院の講義を受けている最中でした。講義が終わって電話をチェックすると、見慣れない番号からの着信履歴が5回ありました。よほど、私に連絡を取りたがってくれたのだと判断し、すぐ、折り返し電話をかけました。ちなみに、私の会社にかかる電話は、私の携帯電話に転送するようになっています。
電話をかけると、電話口の声は、おばあちゃんでした。「道新に載っていた本を買いたいんですけど、どうやって買えますか?」というのが質問でした。「お住まいはどちらですか?」とお聞きすると、「利尻郡利尻富士町です」と言います。北海道の端に住んでいる人が、私の記事を読んでくれたんだと、感動しました。北海道新聞の力を実感しました。
私の本は、全国津々浦々の書店に本を送る取次店を通して販売していないため、利尻郡利尻富士町の住人の方々が行く書店は注文を受け付けないかもしれないと考えました。で、「送料こちら負担で、直接本をお送りできますが、それでよろしければお送りします。お代は銀行に振り込んでいただく形になりますがよろしいですか?」と聞くと、「お願いします」と言います。私は本を丁寧に梱包し、休日でも開いている大きな郵便局に自転車で向かい、おばあちゃんに本を送りました。とても、晴れやかな気分でした。
本を梱包するにあたり、ちょっと気にかかったのが、私の出版社は都市銀行にしか口座を開いていないことです。北洋銀行、北海道銀行や地方の信用金庫を使う方が多い道内の方は、都市銀行の口座への振り込みは面倒と考えてしまうのでは?と考えました。若い方なら、他行の銀行に振り込めることも知っていますが、お年寄りはどうかな? と考えたのです。が、それしか方法がありませんでした。
さて、本を送ってから2週間ほどたっても、銀行に振り込みがありません。もしかしたら、届いていないのかも?と考え、電話をしてみました。おばあちゃんは開口一番「すみません!遅れまして。明日振り込みます」とのこと。「いつでも、お時間のあるときで結構です。本が着いて良かったです」と私。おばあちゃんは、「実は、私、乳がんで・・・」と言います。がんを患って、私の本を読みたいと思ってくだったのだと、胸にじんときました。そして、私は「そうですか、、、。どうぞ、お大事になさってください」と言い、電話を切りました。
さて、それから1週間。気になって、銀行の通帳記帳をしましたが、まだ、振り込みになっていません。 「もしかしたら、私の本は役に立たなかったのかもしれない。だから、代金は払いたくないと思ったのかもしれない」と考えました。少し、落ち込みました。で、夫に伝えると、夫はこう言いました。
「日本人はきちんとしているから、代金を振り込まないなんてことはないよ。きっと、何か事情があるんだよ。そのおばあちゃんに。たとえば、体調が悪いとか、近くに銀行がないとか」
「そうだね、でも、ちょっと落ち込む」と私。
さて、そのことは考えないようにしようと気持ちを切り替えた数日後の5月18日、ポストに郵便が入っていました。そのおばあちゃんからでした。少し厚手の紙の封筒の中には、現金2千円と、一筆を添えたメモ紙が入っていました。演歌歌手「鳥羽一郎」の写真が薄く浮かび上がっているメモ紙でした。「遅くなってすみません。じっくりと読ませていただきました」と書かれていました。
そのおばあちゃんの誠実さに、胸を打たれました。とともに、「私の本は役に立たなかったのだ」と思い、落ち込んでいた気持ちが一気に晴れました。そして、その日一日を気分良く過ごせました。
私は数日後、おつり272円をお礼の手紙とともに、おばあちゃんに送りました。現金書留は520円かかりましたが、誠実なおばあちゃんには、誠実に対応しなければと思いました。
利尻郡利尻富士町のおばあちゃん。ありがとうございました。あなたの電話、あなたの手紙に私は救われました。
You made my day!
たとえば、あなたが落ち込んでいるとき、友人や彼があなたのことを褒めてくれた。もしくは、あなたの子どもや夫が、何気ない、でも素敵なプレゼントをくれることもあるでしょう。一日、仕事や家事・育児で疲れ切ったあなたは、その言葉や小さな贈り物でその日一日を幸せな気持ちで終えることが出来ました。そんなときに、相手に言う言葉です。
「You make my day」-。私はその言葉を最近2回、遠方に住むある人に言いたい気持ちになりました。2回とも、同じ人に対してです。
その人は、北海道利尻郡利尻富士町に住んでいます。4月27日に、北海道新聞に私のインタビュー記事が掲載されたとき、真っ先に電話をくれた人です。その人は記事を読み、拙著「がんと生き、母になる 死産を受け止めて」を読みたいと思ってくれたらしく、直接電話をくれたのです。記事には私の会社の連絡先が書いてありませんでしたので、北海道新聞か書店に電話をして、連絡先を尋ねてくれたのだと推測しました。
電話がきた土曜日の午前中、私は大学院の講義を受けている最中でした。講義が終わって電話をチェックすると、見慣れない番号からの着信履歴が5回ありました。よほど、私に連絡を取りたがってくれたのだと判断し、すぐ、折り返し電話をかけました。ちなみに、私の会社にかかる電話は、私の携帯電話に転送するようになっています。
電話をかけると、電話口の声は、おばあちゃんでした。「道新に載っていた本を買いたいんですけど、どうやって買えますか?」というのが質問でした。「お住まいはどちらですか?」とお聞きすると、「利尻郡利尻富士町です」と言います。北海道の端に住んでいる人が、私の記事を読んでくれたんだと、感動しました。北海道新聞の力を実感しました。
私の本は、全国津々浦々の書店に本を送る取次店を通して販売していないため、利尻郡利尻富士町の住人の方々が行く書店は注文を受け付けないかもしれないと考えました。で、「送料こちら負担で、直接本をお送りできますが、それでよろしければお送りします。お代は銀行に振り込んでいただく形になりますがよろしいですか?」と聞くと、「お願いします」と言います。私は本を丁寧に梱包し、休日でも開いている大きな郵便局に自転車で向かい、おばあちゃんに本を送りました。とても、晴れやかな気分でした。
本を梱包するにあたり、ちょっと気にかかったのが、私の出版社は都市銀行にしか口座を開いていないことです。北洋銀行、北海道銀行や地方の信用金庫を使う方が多い道内の方は、都市銀行の口座への振り込みは面倒と考えてしまうのでは?と考えました。若い方なら、他行の銀行に振り込めることも知っていますが、お年寄りはどうかな? と考えたのです。が、それしか方法がありませんでした。
さて、本を送ってから2週間ほどたっても、銀行に振り込みがありません。もしかしたら、届いていないのかも?と考え、電話をしてみました。おばあちゃんは開口一番「すみません!遅れまして。明日振り込みます」とのこと。「いつでも、お時間のあるときで結構です。本が着いて良かったです」と私。おばあちゃんは、「実は、私、乳がんで・・・」と言います。がんを患って、私の本を読みたいと思ってくだったのだと、胸にじんときました。そして、私は「そうですか、、、。どうぞ、お大事になさってください」と言い、電話を切りました。
さて、それから1週間。気になって、銀行の通帳記帳をしましたが、まだ、振り込みになっていません。 「もしかしたら、私の本は役に立たなかったのかもしれない。だから、代金は払いたくないと思ったのかもしれない」と考えました。少し、落ち込みました。で、夫に伝えると、夫はこう言いました。
「日本人はきちんとしているから、代金を振り込まないなんてことはないよ。きっと、何か事情があるんだよ。そのおばあちゃんに。たとえば、体調が悪いとか、近くに銀行がないとか」
「そうだね、でも、ちょっと落ち込む」と私。
さて、そのことは考えないようにしようと気持ちを切り替えた数日後の5月18日、ポストに郵便が入っていました。そのおばあちゃんからでした。少し厚手の紙の封筒の中には、現金2千円と、一筆を添えたメモ紙が入っていました。演歌歌手「鳥羽一郎」の写真が薄く浮かび上がっているメモ紙でした。「遅くなってすみません。じっくりと読ませていただきました」と書かれていました。
そのおばあちゃんの誠実さに、胸を打たれました。とともに、「私の本は役に立たなかったのだ」と思い、落ち込んでいた気持ちが一気に晴れました。そして、その日一日を気分良く過ごせました。
私は数日後、おつり272円をお礼の手紙とともに、おばあちゃんに送りました。現金書留は520円かかりましたが、誠実なおばあちゃんには、誠実に対応しなければと思いました。
利尻郡利尻富士町のおばあちゃん。ありがとうございました。あなたの電話、あなたの手紙に私は救われました。
You made my day!
2019年5月21日火曜日
大雨の朝、娘の足元には・・・
「ママ、ビニール袋ない?」
大雨が降った今朝、家を出る直前に娘がそう聞いてきました。
「大きさは? 何に使うの?」
「足につけるの」
「???」
娘は「思い付いた」という表情でキッチンへ行き、スーパーの袋が入っているかごから2枚袋を取り出し、玄関へ。そして靴を履きながら、何やらがさごそ・・・。娘と一緒に通勤する夫は玄関の外で傘を差して、娘を待っています。
そして、玄関で靴を履き終わった娘の足元を見て、私は吹き出しました。
「面白い! 待って、写真撮らせて!」とスマートフォンを取りに居間に戻ります。娘はそのまま、玄関の外へ。
外から夫の悲痛な叫び声が聞こえます。
「何なんだ! 恥ずかしいからやめてくれ! それで電車に乗るのか?」
慌ててスマートフォンを取りに行った私は、何とか間に合い、家を出る娘の足元をパチリと写すことができました。
「これなら、濡れないよ」とカメラに向かって微笑む娘。こういう発想が出来て、かつ、こんな姿で登校しようとする娘はすごい!と感動しました。
大雨が降った今朝、家を出る直前に娘がそう聞いてきました。
「大きさは? 何に使うの?」
「足につけるの」
「???」
娘は「思い付いた」という表情でキッチンへ行き、スーパーの袋が入っているかごから2枚袋を取り出し、玄関へ。そして靴を履きながら、何やらがさごそ・・・。娘と一緒に通勤する夫は玄関の外で傘を差して、娘を待っています。
そして、玄関で靴を履き終わった娘の足元を見て、私は吹き出しました。
「面白い! 待って、写真撮らせて!」とスマートフォンを取りに居間に戻ります。娘はそのまま、玄関の外へ。
外から夫の悲痛な叫び声が聞こえます。
「何なんだ! 恥ずかしいからやめてくれ! それで電車に乗るのか?」
慌ててスマートフォンを取りに行った私は、何とか間に合い、家を出る娘の足元をパチリと写すことができました。
「これなら、濡れないよ」とカメラに向かって微笑む娘。こういう発想が出来て、かつ、こんな姿で登校しようとする娘はすごい!と感動しました。
2019年5月18日土曜日
「こどもの日」に改めて自分に言い聞かせたこと
「後でね」と子どもに言わないー。なかなか出来ないことですが、私が日ごろ心がけていることです。以前聴いたアメリカのカントリーソングの歌詞が心に残っているからです。
いつ、どのような場所で聞いたのか、はっきりとは覚えていません。娘が小学校低学年ぐらい、息子がまだ生まれていないか、生まれていても赤ちゃんだったころかもしれません。普段は聴かないラジオを、車の運転中か、自宅でたまたま聴いていたときにかかった歌でした。
その歌を聴いてからというもの、子どもたちに「遊ぼう」と誘われたら、そのときにしていることを中断して遊ぶようになりました。「いま、手が離せないの」とのど元まで出かかっても、手をとめます。その歌詞は、それほど私の胸に深く染み込みました。メロディは全く覚えていません。歌詞だけが、心に残ったのです。
その歌は息子から年老いた父に捧げる歌でした。内容の大筋はこのような感じです。何度も何度も思い返したので、繰り返すうちにフレーズが少し違ってしまったかもしれませんが、この歌の言わんとすることは間違っていないと思います。
僕は小さいころ、父の肩車が大好きだった。
でも、父に「肩車をして」と頼むと、父からは「今、仕事で忙しいんだ。また、今度な」という言葉しか返ってこなかった。やがて、僕は父の肩車に乗りたいと思わなくなり、父の肩車に乗れないほど、大きくなった。
今、老いた父が僕に言う。「たまには一緒に、ご飯を食べないか」。僕は、こう返す。「今、仕事で忙しいんだ。また、今度」
この歌詞が言っているのは、子育てに「今度」はないのだということ。そして、往々にして、子どもは自分が親にしてもらったように親に返すのだということ。
だから、私は思います。息子が、「ママ、公園一緒に行こう」と誘ってくれるのも、娘が「ママ、一緒にケーキを作ろう」と誘ってくれるのも、そのときが最後かもしれないと。実際、思春期の娘は部屋にこもり、好きな音楽を聴いたり、友だちとチャットをしたりすることが多くなり、週末ピクニックや外出に誘っても、来てくれないことも増えました。
今、私は1月に立ち上げた出版社の仕事や4月から通い始めた大学院の勉強に追われています。子どもがこんなにかわいい時期に、様々なことを始めなくても良かったのではないか、と毎日のように思います。でも、私自身の人生の時間も、特に健康で活動できる時間も限られている。だから出来るうちにこれまで人生でやり残したことをしたいという焦りにも似た気持ちもあるのです。
だからこそ、週末や仕事と学校の合間というわずかな時間でも、子どもと過ごす時間を楽しみます。息子と近所の公園に行ったり、お料理をしたり、娘と一緒にガーデニングをしたり、など無理せず、日常生活の延長で出来ることです。
もしかしたら、明日は息子に「公園行こう!」と誘っても、「ママ、今は大丈夫」って言われてしまうかもしれない。娘に「一緒にお料理しよう」と誘っても、「No, Thanks」と言われてしまうかもしれない。娘や息子と過ごしながら、時折、私はその歌詞を心の中で反芻します。そして、改めて、その歌詞を胸に刻むのです。
いつ、どのような場所で聞いたのか、はっきりとは覚えていません。娘が小学校低学年ぐらい、息子がまだ生まれていないか、生まれていても赤ちゃんだったころかもしれません。普段は聴かないラジオを、車の運転中か、自宅でたまたま聴いていたときにかかった歌でした。
その歌を聴いてからというもの、子どもたちに「遊ぼう」と誘われたら、そのときにしていることを中断して遊ぶようになりました。「いま、手が離せないの」とのど元まで出かかっても、手をとめます。その歌詞は、それほど私の胸に深く染み込みました。メロディは全く覚えていません。歌詞だけが、心に残ったのです。
その歌は息子から年老いた父に捧げる歌でした。内容の大筋はこのような感じです。何度も何度も思い返したので、繰り返すうちにフレーズが少し違ってしまったかもしれませんが、この歌の言わんとすることは間違っていないと思います。
僕は小さいころ、父の肩車が大好きだった。
でも、父に「肩車をして」と頼むと、父からは「今、仕事で忙しいんだ。また、今度な」という言葉しか返ってこなかった。やがて、僕は父の肩車に乗りたいと思わなくなり、父の肩車に乗れないほど、大きくなった。
今、老いた父が僕に言う。「たまには一緒に、ご飯を食べないか」。僕は、こう返す。「今、仕事で忙しいんだ。また、今度」
この歌詞が言っているのは、子育てに「今度」はないのだということ。そして、往々にして、子どもは自分が親にしてもらったように親に返すのだということ。
だから、私は思います。息子が、「ママ、公園一緒に行こう」と誘ってくれるのも、娘が「ママ、一緒にケーキを作ろう」と誘ってくれるのも、そのときが最後かもしれないと。実際、思春期の娘は部屋にこもり、好きな音楽を聴いたり、友だちとチャットをしたりすることが多くなり、週末ピクニックや外出に誘っても、来てくれないことも増えました。
今、私は1月に立ち上げた出版社の仕事や4月から通い始めた大学院の勉強に追われています。子どもがこんなにかわいい時期に、様々なことを始めなくても良かったのではないか、と毎日のように思います。でも、私自身の人生の時間も、特に健康で活動できる時間も限られている。だから出来るうちにこれまで人生でやり残したことをしたいという焦りにも似た気持ちもあるのです。
だからこそ、週末や仕事と学校の合間というわずかな時間でも、子どもと過ごす時間を楽しみます。息子と近所の公園に行ったり、お料理をしたり、娘と一緒にガーデニングをしたり、など無理せず、日常生活の延長で出来ることです。
もしかしたら、明日は息子に「公園行こう!」と誘っても、「ママ、今は大丈夫」って言われてしまうかもしれない。娘に「一緒にお料理しよう」と誘っても、「No, Thanks」と言われてしまうかもしれない。娘や息子と過ごしながら、時折、私はその歌詞を心の中で反芻します。そして、改めて、その歌詞を胸に刻むのです。
登録:
コメント (Atom)