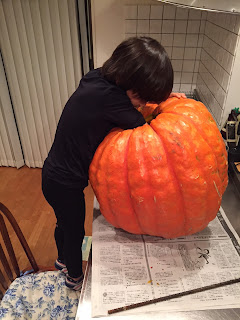「えっ?あんなにおいしそうなのに?」
「うん」
「誰に笑われたの?」
「全員」
大げさなのは父親譲り。おそらくお友達数人に笑われたということでしょう。
「そうなの。どうして皆笑ったの?」
「おにぎりの形が変だって」
「あら、そう。サツマイモがコロコロして可愛いのに」
「変だぁって皆が笑ったの」
このサツマイモは息子が幼稚園でお芋堀りに行ったときに掘ってきたもの。オーブンで焼いたり、大学イモにしたり大切に食べて、細い数本を「さいの目切り」にしてお米と一緒に炊いたのです。その日はちょうど遠足の日。幼稚園の先生から「食べやすいお弁当を」という指示があったので、サツマイモが美味しそうに見えるように小さなおにぎりにして、鶏のから揚げとハッシュドポテトとブロッコリー、うずらの卵と一緒にお弁当に詰めたのです。このサイズのおにぎりはいつも作っていますので、サツマイモがころころーというのが笑いを誘ったのでしょう。
「サツマイモご飯どうだった?」
「すごーくおいしかったよ」
息子との一連の会話を説明します。
「なんか、お友達に笑われたらしくて、落ち込んでいるの」
「へえ、そうなの。笑われたの。私なら、全然気にしないよ」
「そう? ママなら気にするなあ。ママはそんなこと言われたら、”うじうじ”して、悲しいなぁって思う性格」
「ママはうじうじなの? 僕もうじうじ」と新しい言葉を覚えて嬉しそうに会話に入る息子。
「ダディは違うよね。カンカンに怒って、俺が何を食べようと俺の勝手だと言うかも」と娘。3人で大笑いします。
娘は弟に言います。
「おねぇねぇは気にしないよ。笑われたら、そのお友達に『サツマイモご飯嫌いなの? へえ、そうなんだ。私はサツマイモご飯好きだよ』って言うな。普通に」
息子は黙って聞いています。私は「すごいねぇ、平然と言い返せるなんて」と大げさに感心します。
娘は続けます。「きっと、そのお友達、サツマイモご飯いいなあ、僕も食べないなあって羨ましく思っているんだよ。いいなぁって言うのが悔しいから、『サツマイモご飯変だよなぁ』って、隣のお友達も誘って一緒に馬鹿にするのかもよ」
「深いねえ、おねぇねぇ」と私。
「うん。そういうことがあるとよく考えるんだ。何でこの人、こんなこと言うんだろうって」
息子は終始黙って聞いていました。きっと、娘の話がストンと心に落ちたのに違いありません。私の通り一遍の反応より、ずっと説得力のある答えだったように思います。
娘の”模範解答”の後、私は「サツマイモご飯をこれでやめるべきか、もう一度挑戦すべきか」と逡巡しました。幼稚園の先生からは「子供が楽しく食べられるものを」と、お弁当で嫌いな食材を克服させようとするのではなく、楽しく食事をする体験を積み重ねることを重視するよう指導を受けています。
しかし息子が、親の作ったお弁当の中身を恥ずかしいと思うようになっても困ります。私は遠い昔の母の話を思い出しました。伯母が、「お弁当のおかずが恥ずかしかったので隠して食べた、と息子言われた」と苦笑したという話です。伯母はいったい何をお弁当に詰めたか今となっては分かりませんが、たとえどんなユニークなお弁当だとしても、親が愛情を込めて作ったお弁当を隠して食べるというのはいただけません。そして、もう一つ思い出したのが、これも遠い昔、私が高校生だったときの思い出です。
いつものように仲の良い女子たちでお弁当を食べたとき。私の親友が箸でご飯をすくって口に持っていったとき、なんと、そこから細い糸が、、、。ご飯の中に納豆が入っていたのです。しかし、彼女は動じず、箸をくるくる回しながらその糸を取り、「本当にママったら」とくすりと笑いながら食べたのです。私は、このとき親友のおおらかさに深く感動しました。息子にも、親が遊び心で作ってしまった、もしくは「子供が好きだから」と作った、ちょっと変わったお弁当にも動じないように育ってほしいものです。
そんな思いを込めて、後日、もう一度サツマイモご飯を息子のお弁当に入れてみました。「さいの目切り」は同じでしたが、おにぎりにするのは少し酷な感じもしましたので、普通に入れました。
帰宅後に息子に聞いてみました。
「今日のサツマイモご飯、皆に笑われた?」
「ううん、みんなに見えなかったみたい」
「そう、それは、良かったね。おいしかったでしょう?」
「うん、おいしかったよ」
たかがお弁当、されどお弁当。お弁当を通して、子供も親も学ぶのです。